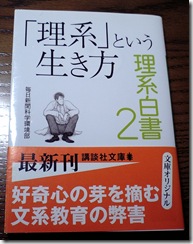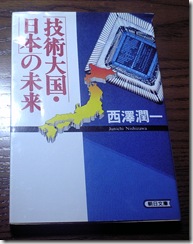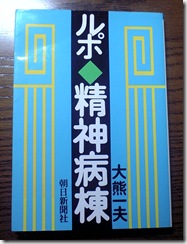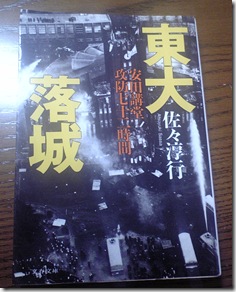今こそ知りたい!とありますが、この本はちょっと古くて2000年1月1日に第一刷が発行されたので、今から9年前の自衛隊の実力という事になります。
この時期の日本は、1998年のテポドン1号の日本上空横断や、1999年3月の能登半島沖不審船事件など、北朝鮮の脅威が明確化し、世論は緊張状態にありました。その後も幾度も国防上の問題に直面しましたが、緊張は9年たった今も継続中といっても過言ではなく、「今こそ知りたい!」は現在も「今こそ」です。
軍隊の実力はそう早く劇的に変わるものではないので、今読んでも意味のある内容だと思います。
巻頭には付録で報道カメラマン宮嶋氏による自衛隊の訓練の様子を撮った写真が載っています。過酷な訓練にも同行する熱血肌の宮嶋氏の独特な文章と、密着取材の果てに撮られた写真は見ごたえがあって面白いです。
内容は、他国が攻めてきた時の対応と、自衛隊の行動限界に焦点をあてて書かれています。自衛隊の兵器や隊員の実力はもちろんのこと、法整備に関する検討もされています。武装船が襲来したらどうなるか、破壊工作部隊が侵入したらどうなるか、などいろんな場合を想定したシミュレーションが面白いです。
読んだ感想は、自衛隊そのものは頼もしいものがありますが、法や政府、世論、マスコミが国防に向いてないと思いました。情報収集処理能力は1990年代まではかなり貧弱でしたが、現在は能力が向上し、合理化が進んでるようです。
有事になったら一般市民がどうこう出来るというわけではありませんが、世論を構成する一個人として、現状を把握するには十分な本だと思います。自衛隊豆知識もかなりたまって面白かったです。